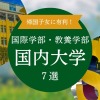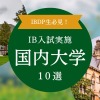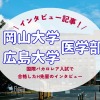【法政大学GIS学部長インタビュー】IBでの探究心を世界レベルへ!英語でリベラルアーツを学ぶ魅力とは?

みなさんは、法政大学グローバル教養学部(GIS)をご存知でしょうか?
法政大学GISはグローバルリーダーの育成を目指し、2008年に設立。英語によるリベラルアーツ教育を実践してきました。
この記事では法政大学GIS学部長である福岡賢昌教授へのインタビューを通じて、GISのリベラルアーツ教育の真髄、IB教育との親和性、そして学生に求める資質について深く掘り下げます。
法政大学GISに興味がある方、大学でリベラルアーツを学びたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
法政大学グローバル教養学部について
法政大学グローバル教養学部(以下、GIS)はグローバルリーダーとして社会で活躍できる人材の育成を目指した学部です。2008年に設立され、15年以上にわたり英語によるリベラルアーツ教育を実践してきた豊富な経験とノウハウがあります。GISはグローバルリーダーを育成するための6つの素養、「高い英語力」「文化的知性」「幅広い知識教養」「高度な専門知識」「実践的スキル」「人間力」を養う教育を行っています。
高い英語力:最低でもTOEFL100点、IELTS7.0〜7.5程度の英語力
文化的知性:文学、歴史、哲学、心理学、言語学、国際関係学、経営学等に関する幅広い基礎的な知識教養
幅広い知識教養:複数の文化の中で自分と異なる文化を持つ人たちと一緒に仕事をする能力
高度な専門知識:問題発見・解決力、批判的・創造的思考力、ディスカッション・プレゼンテーション能力、チームワーク、共感力
実践的スキル:高度な学術的専門知識(修士/博士課程)に繋がる基礎的な専門知識(学士課程)
人間力:熱意と責任感をもって文化を超えて様々な人たちと交流し、多様性あるチーム等を率いることができる人間的な魅力
GISではこれらの素養を高めるために、英語によるリベラルアーツ教育を導入しています。
リベラルアーツカリキュラム
GISは人文学・社会科学・ビジネス分野を中心とするリベラルアーツ教育を行っています。約30の学術分野で200以上の科目を提供しており、興味や知識のレベルを選んで授業を受けることができます。まず、1年次には複数の専門分野を横断的に履修して幅広い視野を養い、その後3年次からのゼミで特定の専門分野を掘り下げ、深い専門性を追求します。学生は自身の関心に基づき、さまざまな分野の科目を組み合わせながら履修しますが、3年次以降はゼミ活動を通じて研究テーマを掘り下げ、最終的にはゼミ論文の執筆を通じて、問題の発見・分析・論述に至るまでの一連の力を養成します。
全ての講義が英語で行われる
GISは200以上の全ての講義が英語で実施されます。これは教授が英語で講義を行うというだけではなく、講義内のディスカッションやプレゼンテーション、また、レポート等の課題も全て英語で行われます。また、首都圏において、学部全体として英語でリベラルアーツを学べるのは、GISを含め、数えるほどしかありません。一部の科目や特定のプログラムだけでなく、学部全体で提供しているため、学生は4年間、英語で思考し学ぶ環境に浸ることができます。
少人数教育
GISにおける1クラスの受講人数は20〜25人です。多くのIB認定校が、対話や探究を中心とした質の高い授業のために20名前後の少人数教育を実践していますが、GISもまさにそのスタイルを共有しています。授業は常に、学生の主体性を引き出すディスカッションやプレゼンテーションで構成されており、IBで培った探究心をさらに発展させることができる環境です。教員との距離が非常に近いため、学生それぞれの個性や学術的関心まで深く理解した上での的確なサポートが提供できます。
海外大学院への進学&就職サポート
GISでは4年間の学部で取得する学士からさらに、将来的に修士以上の学歴を取得することを推進しています。主に海外大学院への進学を視野に入れており、GSASと呼ばれるサポートも存在します。そのため、学生はGISで基礎知識をしっかりと身につけ、その上で海外大学院へ進学するということが可能です。また、就職する学生へのサポートもGISの産学連携組織(主に日系および外資系グローバル企業に勤務するビジネスパーソン、政府関係者、起業家等で構成)であるGGLIを中心に提供しています。
福岡学部長の紹介

インタビューにご協力いただいたのは、2023年4月に法政大学グローバル教養学部(GIS)の学部長に就任した福岡賢昌教授です。東京工業大学で博士号を取得。情報・通信業界(NTT東日本、NTTコミュニケーションズ)で国際的な戦略立案やマネジメントに従事。専門は国際経営学(戦略的提携、交渉、ブランド戦略など)です。2016年には台湾の大学に招かれ、ブランドマネジメントに関する講義を行った経験もあります。法政大学GISでは准教授を経て2020年に教授となり、2021年~2022年、カリフォルニア大学バークレー校(UCB)の客員研究員を経て、現在は学部長としてアカデミックな知見とビジネスにおける実践的な経験を活かしながら、次世代のリーダー育成に取り組んでいます。
福岡学部長へのインタビュー

Q1:GISが考えるリベラルアーツとはなんでしょうか?
GISが考えるリベラルアーツとは、単に幅広い教養を身につけることではありません。複雑化する現代のグローバルな課題は、単一の学問分野では解決不可能です。GISでは、様々な学問分野の知識やアプローチを身につけ、批判的思考を駆使して、多様な専門家を束ねながら問題解決を主導できる「グローバルリーダー」を育てることを目指しています。
Q2:福岡学部長がGISの運営に関わる中で、最も「GISらしさ」を感じられる瞬間やエピソードはありますか?
GISの学生たちが、英語で自らの意見を論理的に主張し、他者の異なる価値観や文化的背景に対して敬意をもって接して、リーダーシップをとっている姿を見ると、まさに本学部の目指す「グローバルリーダー」を体現されていると感じます。
また、授業外でも、国際問題や社会問題について学生同士が自主的にディスカッションを行い、また、イベント等を企画・運営している様子は、学びが単なる知識の習得にとどまっていない証だと思います。また、GISの学生たちの日常は、日本語と英語が自然に混ざり合うバイリンガルな環境そのものです。友人との会話の中で、話題や相手に応じて言語を瞬時に切り替えており、教室の外でもグローバルなコミュニケーションが実践されています。
Q3:福岡学部長が大切にしている教育理念や価値観があればお聞かせください。
私自身が教育理念として大切にしているのは、「グローバルマインドセット」と「文化的アイデンティティの尊重」の両立です。グローバルスタンダードに基づく広い視野と柔軟な思考を持つと同時に、それぞれのルーツや文化を誇りに思い、それを他者に対しても丁寧に説明できる力を育んでほしいと考えています。また、高い視点で物事を捉える「俯瞰」と低い視点で物事を捉える「仰視」も大切にしています。グローバルな文脈で物事を俯瞰的に捉える力と、国内の課題や文化に対して深く学び、敬意をもって見つめる仰視の姿勢。この二つを行き来できる思考の柔軟さこそが、これからの時代を生きる上で必要なことだと思います。
Q4:IBで培われた学習経験が、同学部のどのような教育プログラムや環境で活かされ、さらに伸ばしていくことができるとお考えですか?
IBで培われた探究スキルや批判的思考、多文化理解は、まさにGISの学びと親和性が高いです。特に、GISでは講義の多くにディスカッションやグループワークが組み込まれており、異なるバックグラウンドを持つ学生たちと対話しながら、多角的な視点で物事を考える力が自然と鍛えられます。
Q5:全ての授業が英語で行われるとのことですが、入学時点では学生の英語力に幅があると思います。英語でのアカデミックな議論や論文執筆についていくために、学部としてどのようなサポートや工夫をされていますか?
入学当初、学生の英語力にある程度の幅がありますが、高校で学習習慣を身につけた学生であれば、最初の1年間で十分に慣れ、英語によるアカデミックな学びに対応できるようになります。なぜなら、GISでは、1年次に「英語で学ぶ力」を集中的に伸ばすことを目的として、学生の英語力に応じたレベル別のアカデミックスキル科目を設けており、アカデミックな講義に十分な英語力がまだ備わっていない学生にも対応できるよう配慮しているからです。このサポートにより、2年次には多くの学生がアカデミックな議論やプレゼンテーションにも積極的に参加できるようになります。

Q6:GISには様々なバックグラウンドを持つ学生が集まりますが、多様な価値観を持つ学生たちが共に学ぶ「共創の場」を創り出すために、学部としてどのようなことを重視していますか?
GISにおける「多様性」とは、無秩序を意味するのではなく「共通のルールを前提とした違いの尊重」であるという認識が大切です。まずは、全員が安心して発言し、参加できるための土台として、ルールの存在とその意義を伝えた上で、授業においてはグループワークを積極的に取り入れ、異なる文化的背景や価値観を持つ学生同士が意見を交わし、相互に学び合う環境を重視しています。そうしたプロセスを通して、学生たちは異なる意見を否定せず、むしろそこに新たな視点を見出す「気づき」や「越境の学び」を体験しています。
Q7:福岡学部長ご自身が、グローバル教養学部で学生たちに最も身につけてほしいと願う資質はなんでしょうか?
広い視野:決して井の中の蛙にならず、自らの常識や文化が唯一無二だと思い込まないことです。他者の価値観や背景に対する理解を深めて欲しいと思います。
実行力:「〜すべき」と語るだけの人間にならず、実際に行動に移せる力を育んでほしいです。知識を得た先に、社会でそれをどう活かし、何を変えられるかを常に問い、自らの手で形にする姿勢が大切だと考えています。
よりよい社会にするための一役を担っているという自覚:個人の成功だけを追い求めるのではなく、自分が社会の一員として、周囲にどう貢献できるかを考える力を持ってください。当事者意識を持ち、他者を巻き込むリーダーシップこそが重要です。
俯瞰と仰視の往復:物事を全体から俯瞰して見る視点と、仰ぎ見る視点の両方を意識的に行き来する思考習慣を身につけてほしいです。それにより、冷静さと情熱を併せ持った判断力が育ちます。
Q8:最後に、GISへの進学を考えている帰国子女やインターナショナルスクールの生徒たち、特にIBプログラムで学んでいる生徒たちに向けてメッセージをお願いします。
IBプログラムやインターナショナルスクールで学んできた皆さんが持つ、探究型の学びの経験は、まさにGISが重視する資質と合致しています。私たちは「問題を解く力」だけでなく、「問いを立てる力」を重視しています。つまり、正解を覚えるだけでなく、なぜそれが課題なのか、どのような文脈で意味を持つのかを問い直す視点を大切にしています。
GISでは、学際的な視点をもとに、グローバルな課題を自ら設定し、他者と対話しながら探究できる学生を歓迎しています。IBで養われた主体性、批判的思考、多様性への理解は、学部内でも大きな強みとなるでしょう。入試準備においては、これまでの経験(リーダーシップ経験や探究経験など)や興味関心を、具体的に言語化し、自分がどのような学びをGISで追究したいのか、どのように社会に貢献したいのかをしっかり伝えることを意識してください。皆さんの探究心が、GISでの学びをさらに豊かなものにしてくれると信じています。
GISに入るには?
IB生がGISへ入学するためには自己推薦入試のS基準、またはA基準を利用することがおすすめです。詳しい情報は、大学の公式サイトをチェックしてください。
元IB生によるインタビューの感想
今回、GISの教育について深く知る目的で、福岡学部長にインタビューをさせていただきました。お話を伺い特に感銘を受けたのは、GISの全ての教育要素が「実践的なグローバルリーダーの育成」という、明確な一つのゴールに向かって戦略的にデザインされている点です。
IBで培われる探究心や批判的思考力、問いを立てる力、そしてGISが提供する英語でのリベラルアーツなど、その全てが単独で存在するのではなく、グローバル社会のリーダーを育成するという大きな目標のために強く結びついているのだと理解しました。
GISでは、IBで培われたATLスキルを十分に活かせるのはもちろん、知識と思考を獲得することでそのスキルを社会でどう活かすかを学ぶのがGISなのだと実感させられる、大変有意義なインタビューでした。
福岡賢昌学部長、お忙しい中インタビューにご協力いただき、本当にありがとうございました。
最後に
いかがでしたでしょうか。
今回は法政大学グローバル教養学部の紹介、そして学部長へのインタビューをお届けしました。興味を持たれた方はぜひ法政大学、またはグローバル教養学部のホームページをご覧ください。