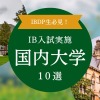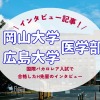【IB受験体験談】上智大学 Green Scienceに理工学部英語コース入試で合格したHさんにインタビュー!
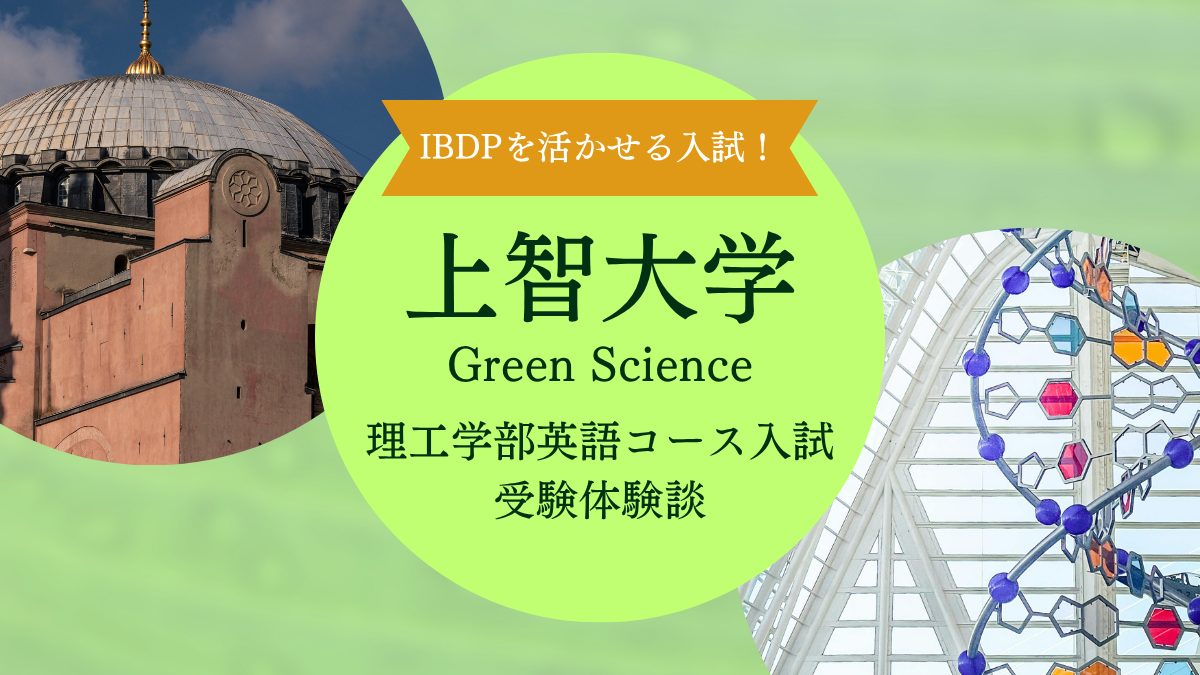
今回は、上智大学の理工学部に設置されている英語で学べるプログラム「Green Science」に在籍するHさんにインタビューしました。大学選びから、IBと両立しながらの受験対策、そして実際に出願を終えてから合格までの道のりについて、お話を伺いました。国内大学の英語学位プログラム、特に理系への進学を検討しているIB生の皆さんは、ぜひ参考にしてください!
上智大学 Green Scienceについて
Green Scienceとは?
上智大学理工学部には、英語で授業が行われるGreen ScienceとGreen Engineeringの2つのコースがあります。どちらのコースも、現代社会が直面する環境問題やサステナビリティに関する課題に対し、科学技術の視点から解決策を探求することを目的としています。
Green Scienceでは、物質生命理工学科と機能創造理工学科の分野を横断的に学び、理学の基礎を固めながら、環境問題への理解を深めます。幅広い科学的知識を基に、持続可能な社会の実現に貢献するための能力を養います。
理工学部英語コース入学試験について
この入試は、書類選考のみで合否が判定されます。IBディプロマ資格(または見込み)を持つことが出願資格の一つとなっており、IB生にとっては対策しやすい入試形態と言えるでしょう。選考では、IBの成績に加え、エッセイや推薦状などが総合的に評価されます。出願期間は年に2回(First Application / Second Application)設けられており、自身の学習計画に合わせて柔軟に出願スケジュールを組むことが可能です。
インタビュイーのプロフィール
| 所属大学・学部 | 上智大学 Green Science 1年生 |
|---|---|
| 受験大学 (併願校) | 早稲田大学 国際教養学部 |
| 出身高校の区分 | 海外インターナショナルスクール(ベトナム) |
| 最終試験 受験時期 | 2025年5月 |
| IB選択科目・スコア | HL: Math AA (5), Chemistry (7), English (6) SL: Biology (6), Geography (6), Japanese A (6) TOK/EE (Biology): 2 Total: 37 |
| これまでの教育歴 | 中学2年生まで日本、その後高校卒業まで海外インター |
| 高校時代に取り組んでいたこと | 水泳部、生徒会(Grade 11から) |
上智大学 Green Scienceの受験体験談: 大学選び編
まず、理工学部を志望した理由について教えてください。 何か将来の目標はありますか?
もともと理系科目が得意だったので、大学では理系の道に進もうと決めていました。ただ、その時点では「これをやりたい」という明確で具体的な将来の夢があったわけではありません。高校の生徒会でサステナビナビリティに関する活動に取り組む中で、自分の得意な化学と関連付けられる分野に興味を持つようになりました。環境問題など、より広い視野で理系の学問を探求したいと考えたのが、理工学部を志望した最初のきっかけです。
併願校も含め、数ある大学の中からどのようにして出願校を絞り込んでいきましたか?
高校在学中は海外大学も選択肢にありましたが、IBの勉強と並行して奨学金制度を調べたり、複雑な出願プロセスを進めたりすることのハードルの高さを感じ、断念しました。長年英語で学んできたため、今から日本の大学の一般受験のために日本語で学び直すのも難しいと感じ、英語で理系の学問を追求できる日本の大学に絞りました。その中で、自分の興味関心と合致するプログラムを提供していたのが上智大学と早稲田大学でした。
理系の英語で学べるプログラムは国内外に多くある中で、最終的に上智大学理工学部への進学を決めた理由を教えてください。
最終的には、早稲田大学の国際教養学部と上智大学のGreen Scienceでかなり悩みました。大学のネームバリューや、幅広く学べる国際教養学部の魅力も感じていましたが、やはり自分が最も探求したい「化学とサステナビリティ」という分野を専門的に学べる点に強く惹かれました。物理やコンピュータサイエンス系よりも、基礎科学をじっくり学びたいという自分の希望に、Green Scienceのカリキュラムがぴったり合っていると感じたのが決め手です。
上智大学理工学部の英語コースに関する情報は、どのように集めましたか? 特に役立った情報源があれば教えてください。
私の通っていたインターには日本人が少なく、上智大学に進学した先輩もいなかったため、学校の先生から直接的なサポートを得ることは難しかったです。また、オープンキャンパスの時期に日本へ一時帰国することもできず、対面での情報収集はできませんでした。そのため、主な情報源は大学の公式ウェブサイトと、大学が公開しているYouTubeチャンネルでした。特にGreen Scienceに関する情報は限られていましたが、それらの数少ない情報を頼りに、自分に合うプログラムかどうかを判断していきました。
海外在住のIB生にとって、日本の大学の情報収集はHさんのようにオンラインが中心になることが多いでしょう。特に英語学位プログラムは情報が限られている場合もあるため、公式サイトを隅々まで読み込み、少しでも多くの情報を得ようとする姿勢が大切になります。
ご自身の興味があった研究分野について、上智大学の先生や研究室が特に魅力的だと感じた点はありましたか?
出願エッセイを書くにあたって、Green Scienceの先生方の研究内容をウェブサイトで調べました。特定の先生のこの研究がやりたい、という具体的なものまでは固まっていませんでしたが、多くの研究が環境問題に直接関連している点に非常に魅力を感じました。生徒会活動で取り組んできたサステナビリティの課題に対して、より科学的かつ具体的にアプローチしている研究が多く、大学で学ぶことへの期待が大きく膨らみました。
上智大学 Green Scienceの受験体験談: 受験対策・受験編
選考にあたって
出願書類の準備は、いつ頃から具体的に始めましたか?IBの勉強との両立で工夫した点があれば教えてください。
最終学年の9月頃に上智大学を受験することを決め、そこから本格的に準備を始めました。10月頃からエッセイを書き始め、推薦状も先生に早めにお願いしました。私の学校は、自分から積極的に動かないとサポートが得られにくい環境だったので、先生との関係性を普段から良好に保ち、早めに相談することを心がけていました。IBの勉強との両立については、1日のスケジュールを細かく決めて、ルーティン化することで乗り切りました。
出願に必要なテストスコアはどの試験のスコアを提出しましたか?
IB DiplomaのPredicted Gradeを提出しました。SATなど他の標準テストは受験しませんでした。上智大学のこの入試では、IBのスコアが非常に重要視されていると感じています。
英語能力試験のスコア提出は免除でしたか? もし提出していればどのスコアを提出したか教えてください。
免除ではなく、IELTSのスコアを提出しました。Grade 11の時に取得したスコアがあったので、それを使いました。
スコア取得に向けて、IBの英語の勉強以外に行った対策があれば教えて下さい。
スコアは6.5とそれほど高くはありませんでしたが、上智大学の出願ではそこまで重要視されていない印象でした。対策としては、IBの英語の授業とは別に、IELTSの過去問を数回分解いて、試験の形式に慣れることに集中しました。併願していた早稲田大学の方がIELTSのスコアを重視する傾向があったため、そちらの対策のためにもう一度受験し直しました。
出願書類: エッセイについて
理工学部英語コース入学試験では、500語程度のエッセイの提出が求められます。テーマは以下の3点です。
- 志望理由
- 将来の目標とのつながり
- 魅力を感じた点
「志望理由」では、ご自身のどのような経験や関心を、医学への興味や将来の希望に結びつけて記述しましたか?
「志望理由」では、単に大学で学びたいことを書くだけでなく、自分の強みをアピールすることを意識しました。ベトナムでの生活を通して環境問題を身近に感じた経験や、生徒会でのサステナビリティに関する活動経験を具体的に記述しました。IBでの学び自体には深く触れませんでしたが、これらの経験を通して培われた問題意識が、Green Scienceで学ぶ動機に繋がっていることを示しました。
「将来の目標とのつながり」ではどのような内容を執筆しましたか?
ここでは、自分が抱いている環境問題への関心を、より具体的に将来の目標として示しました。大学のウェブサイトを参考に、Green Scienceコースが掲げる教育目標と自分の目標が一致していることを強調しました。「環境問題をなくしたい」という漠然とした思いだけでなく、大学での学びを通してそのための専門的な知識とスキルを身につけたい、という意欲を伝えられるように工夫しました。
「魅力を感じた点」について、書いた内容や特に自信をもって書いた項目があれば教えて下さい。
この項目では、事前に調べた教授の研究内容に具体的に触れました。数ある研究の中から特に自分の興味と合致するものを選び、「私もこのような研究に挑戦してみたい」という熱意を伝えました。自分の言葉で書くというよりは、大学のウェブサイトにある情報を活用し、いかに自分がそのプログラムを深く理解し、魅力を感じているかを客観的な事実に基づいて示すことを心がけました。
3つの項目を500語にまとめるのは大変でしたか? 執筆を進めるうえで行った工夫があれば教えてください。
はい、とても大変でした。IBのエッセイは1200語以上が普通だったので、500語という文字数制限は非常に短く感じました。最初は文字数を気にせず、書きたいことを全て書き出しました。そこから、最も伝えたい核心部分は何かを考え、重要な要素だけを残して削っていく、という作業を繰り返しました。伝えたいことはたくさんありましたが、いかに簡潔に、要点をまとめて表現するかを工夫しました。
指定された文字数の中で、いかに自分の魅力を最大限に伝えるかが、大学受験のエッセイにおける共通のポイントとなります。まず自由に書き出してから削っていくという方法は、思考を整理し、本当に重要な要素を見極める上で非常に有効な戦略だと言えるでしょう。
IBでの経験を出願書類でアピールする際に、理工学部での学びにどう繋げて説明しましたか?具体的なエピソードがあれば教えてください。
IBのEEやIAといった学術的な経験よりも、CASでの活動をアピールしました。特に、ボランティア活動や、個人的に取り組んでいたヨガのインストラクター資格取得といった、他の人があまり書かなそうなユニークな経験を盛り込むことを意識しました。これらの活動を通して得られた多様な視点や行動力が、理工学部での学際的な学びにも活かせると考えました。
エッセイを書き上げるまでに、何回ほど推敲しましたか?また、完成に至るまでに誰かに読んでもらい、フィードバックはもらいましたか?
学校の英語の先生、大学カウンセラー、そして家庭教師の先生という、立場の異なる3人の方に読んでもらいました。英語の先生からは文法的な視点で、カウンセラーの先生からは大学出願エッセイとしての構成について、それぞれ的確なアドバイスをいただきました。複数の視点からのフィードバックをもとに、2〜3回ほど大きな修正を重ねました。出願を決めてから1ヶ月以内という短い期間で、集中的に書き上げました。
書類を全て提出し終えてから、合格発表までの期間はどのような心境で過ごしましたか?IBの最終試験も近い時期だったかと思いますが、どのように気持ちを切り替えていましたか?
出願後は2〜3ヶ月ほど時間があったので、最初のうちは結果のことばかり考えてしまい、落ち着きませんでした。しかし、IBのMockや最終試験が近づくにつれて、そちらに集中せざるを得なくなりました。一度出願したからには、あとは結果を待つしかないと気持ちを切り替え、目の前のIBの勉強に全力を注ぐようにしました。「一旦忘れる」ことが、精神的なバランスを保つ上で重要だったと思います。
IBスコアについて
IBのスコアに関して、より高得点を獲得するために、どのような学習戦略を立てましたか?
Green Scienceに進学するためには、やはり理系科目のスコアが重要だと考え、重点的に学習時間を割きました。特にHLで選択していた数学と化学は高い点数を目指し、毎日欠かさず勉強する時間を作っていました。SLの科目も、苦手意識を持たず、最低でも6点を取れるように目標を設定し、バランス良く学習を進めることを意識しました。
特に科学3科目と数学の学習で意識したことを教えてください。
Math AA は最も難しい科目だと感じていたので、IBが始まってから毎日、朝の時間を数学の勉強に充てるというルールを決めていました。オンライン学習ツールのRevision Villageも早い段階から活用し、継続的に問題演習を重ねました。化学は過去問を繰り返し解くことで問題のパターンを掴み、生物は暗記が中心だったので、マインドマップなどを作るよりも、効率を重視して覚えることに徹しました。
学校から提示されたPredicted Gradeには満足していましたか?
Predicted Gradeは37点で、大学が示していた合格者の平均スコア (38点) より少し低かったので、正直焦りました。しかし、大学の説明会動画で「あくまで平均であり、それ以下のスコアで合格している学生もいる」という話を聞いていたので、そこを信じて出願しました。結果的に、このPredicted Gradeで合格をいただくことができました。最終試験の結果は、合格後に提示される最低限のスコアを満たせばよかったので、精神的なプレッシャーは少なかったです。
推薦状について
推薦状は誰に執筆を依頼しましたか? 理由も併せて教えてください。
HLで選択していた化学の先生と、IBコーディネーターの先生の2人にお願いしました。理系の学部なので、理系科目の先生に1人はお願いしたいと考えていました。その中でも、最も自分のことをよく理解してくれていて、関係性が良かった化学の先生を選びました。IBコーディネーターの先生は、IBプログラム全体を統括しており、大学進学についても詳しかったため、もう1人としてお願いするのに最適だと考えました。
上智大学 Green Scienceの受験体験談: 最後に振り返って
大学受験の際、IBをやっていて良かったと感じたことはありますか?
IBの学習は本当に大変でしたが、日本の一般受験と比べると、精神的には楽だったのではないかと感じています。全て書類選考で完結するので、一発勝負の試験がないのは大きな利点でした。また、IAやEEで培ったエッセイライティングのスキルは、今回の出願エッセイ作成に直結しましたし、CASでのボランティアや生徒会活動といった経験が、自分だけのアピールポイントになったと感じています。IBを通して、自分の好きなことを見つけられたのも大きな収穫でした。
最後に、これから上智大学 Green Scienceを目指すIB生の後輩たちへ向けて、「これだけはやっておいた方がいい」というアドバイスをお願いします。
理系が好きで、かつ英語で幅広く学びたいという人には、Green Scienceはとても良いプログラムだと思います。IBの勉強との両立は大変だと思いますが、IBで学んだエッセイを書く力や探究する力は、間違いなく大学での学びに繋がります。アドバイスとしては、勉強以外にも何か夢中になれることを見つけて、アピールできる材料を増やしておくことをお勧めします。ボランティアなど、少し視野を広げて活動してみると、それが巡り巡って自分の強みになるはずです。応援しています!
まとめ
生徒会活動から自らの興味を見つけ、限られた情報の中で大学の研究内容まで深く掘り下げてエッセイに繋げたことが、Hさんの大きな合格の秘訣と言えるでしょう。また、学業成績だけでなく、CASや個人的な活動をユニークな強みとしてアピールすることも、書類選考で個性を際立たせる上で重要です。IBで培った力は、受験だけでなく、その先の大学生活でも必ずあなたの武器になるはずです。応援しています!