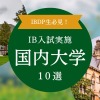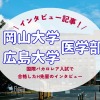IB生の保護者2名にインタビュー!「親にできるサポートってなんだろう?」
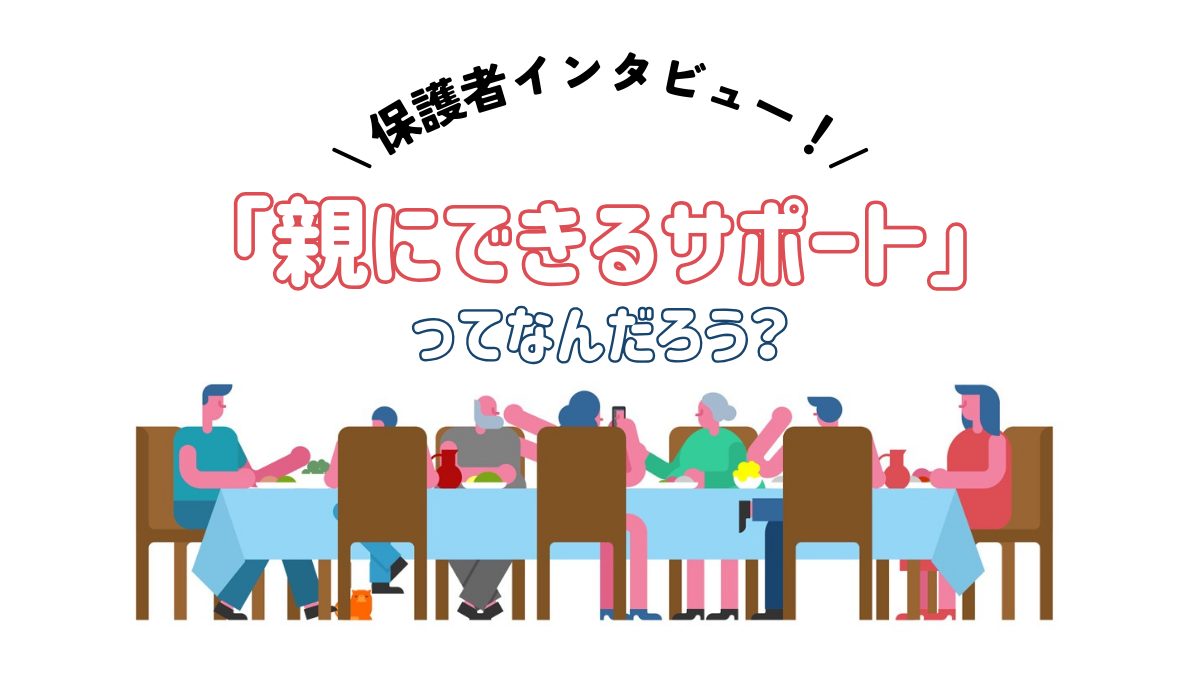
2024年5月にUniv-it!会員の皆さまにご協力いただいたアンケートの中には「保護者としてIB生をどうサポートできるのか?」といった疑問が多くありました。
独自のカリキュラム・評価方法という特徴を持つIBを履修する高校生にどこまで踏み込んだサポートをして良いのか、という不安を抱える保護者の方も多いと思います。
そこで今回は、海外でIBを履修したお子さんを持つ保護者の方に聞いた体験談をインタビュー記事としてまとめてみました。保護者の方々はもちろん、現役IB生にとっても保護者の気持ちを知ることができる一本になっていますので、ぜひご一読ください。
- 1. 今回お話を伺ったお二人のお子さんの基本情報
- 2. Q1:お子さんがIB生だった頃、IBのことはどのくらい理解していましたか?
- 3. Q2: IB生の保護者として抱えていた不安や疑問点などはありましたか?
- 4. Q3:DPとCertificateの選択にどのように関わりましたか?
- 5. Q4:どのようにお子さんをサポートしていましたか?また、その際に何か気をつけていたことはありますか?
- 6. Q5:学校や先生方とのコミュニケーションは積極的に取るようにしていましたか?
- 7. Q6:IB生はタイムマネジメントが求められる、とよく聞きますが、この観点から保護者にできるサポートはあると思いますか?
- 8. Q7:お子さんの大学受験や進路決定にはどの程度関わっていましたか?
- 9. Q8:最後に、何かこれまで伺ってきた内容以外で話せることがあれば教えてください。
- 10. 最後に
今回お話を伺ったお二人のお子さんの基本情報
| Nさん |
|
|---|---|
| Kさん |
|
Q1:お子さんがIB生だった頃、IBのことはどのくらい理解していましたか?
Nさん「知らない状態だった」
| 初期はほとんど知らず、「IBとは一体何か」Grade 10(Pre-IB)の間に徐々に調べ始めました。リサーチを始めた理由は個人的な興味と、保護者として必要性を感じたことにありました。必要性というのは、子供の「科目選択」についてです。「ここでミスすると大変なことになる!」、自分も知っておかないと、と思いました。
そこからはEDUBALをはじめとする情報サイトなどをくまなくチェックしましたし、学校の先生によってどの教科だと点数が取りやすいという点についても上の学年のお母さんたちと何とかコネクションを持って「どんな科目を選んでいるのか、どんな授業が提供されているのか」聞いたりもしました。 |
Kさん「全く知らなかった」
| IBについて全然理解していない状態で、通うことになるインター校がIB校ということもしっかりとは認識していませんでした。IBの教育は日本の一般的な物とは違ってレポートが多かったりすると思うのですが、それも把握していなかったです。 今思うと「もっと理解しておけばよかったな」と。例えば、かなり高い英語力が必要、ということも 転入してから徐々に気づきました。先に知っていれば、日本にいる時に英語力をもっと上げる対策が取れたな、と思います。 |
Q2: IB生の保護者として抱えていた不安や疑問点などはありましたか?
Nさん「評価方法の曖昧さについて」
| 何が評価につながるのか見えづらい・わかりづらい教科や課題がある、というのは保護者としても不安でした。どうサポートできるのかもわからない領域ですし。日本の教育とは全く違うっていうのは大前提としてわかるし、頑張っているのに評点が取れないというもどかしさを娘が抱えているのを感じました。 |
Kさん「漠然とした不安感・スケジュール管理について」
| 情報がないことによる漠然とした不安がありました。振り返るともっと情報を集めておくべきだったな、と思いますね。 他には、日本の大学受験とIBの勉強のタイムスケジュール管理が難しいと感じていました。元々高校3年生の時に日本に帰国する予定だったのですが、それが延びて卒業まで在籍することになったんです。DPとCertificateどちらを選ぶのかによって大学受験の方式も変わってくるので、不確定要素への不安というのもありました。 |
Q3:DPとCertificateの選択にどのように関わりましたか?
Nさん「2つの違いと受験への影響を情報収集・最終判断は子供に」
| DPとCertificateどちらにするのかという点が1番悩みましたし、両方の選択肢があることもインター校選びの際の大きなポイントになりました。 ただ、日本にいた時から「インター校や現地校の経験なしに、高1から3年間でDP取得は難しいと思う」と言われていたこともあって、「IBDPを履修できる英語力はあるのか?」については塾や学校と相談を重ねました。そういうプロセスを踏まえて、最終的には娘自身が「DPはやめる」という決断をしました。 最終的に出たスコアを見て振り返ると「やっぱりDPいけたかもな」という思いはあるみたいです。 |
Kさん「親として提案しつつ子供に決定権」
| 最終的にDPにすると決めたのは子供でした。 息子は英語がそれほど得意なわけではなかったので、「もしも落ちてしまった時に何も残らないんじゃないか」という不安がありました。「それならCertificateにして、帰国生入試などに向けた小論文対策やTOEFL対策に時間を充てた方が良いのではないか」ということを子供にも提案しましたが、周りの友人がほとんどIBに進むという学校の環境もあり「自分もDPに進みたい」と。たとえDPが取得できなかったとしても履修することによる強みはあるのではと思います。息子は総合型選抜で合格したのですが、EEの内容などをアピールできたので、志望理由などと繋げられた点は強いのかなと。もしDPが取れていなかったとしても、EEやIAに取り組んだという経験はあるので、そのあたりを見てもらえるんじゃないかなと思いますね。 |
Q4:どのようにお子さんをサポートしていましたか?また、その際に何か気をつけていたことはありますか?
Nさん「IBの勉強以外のサポートを」
| 勉強面は基本的にタッチできないので、お友達に聞くなり、先生に頼ってもらいました。保護者はその他情報収集・健康面(メンタル、食事)のサポートしかできないですよね。プレゼンの準備中でネガティブになっている時には「大丈夫!」と励ましたり。あとは笑いをとる!(笑)試験期間中はピリピリする時が多いと思うので、ちょっとでも力を抜けるように大事にしていたことのひとつです。
その他だと、レポート案を考えることには協力したことがあります。例えばJapaneseだと「これとこれを繋ぎ合わせてうまく組み立てるには、どうしたらいいんだろう」と家族でディスカッションしたり。娘は抱え込めなくなった時に家族に助けを求めてくれる子だったので、そういうタイミングで「今こういうのをやってるんだ」と知ることもできました。わかる範囲・できる範囲で相談に乗ったりはしました。 |
Kさん「大学受験のサポートを中心に」
| IBの学習は親にはサポート出来なかったので本人に任せるしかありませんでした。 子どもは日本の大学に進学希望だったため、自宅では小論文対策として、一緒にニュースを深掘りしたり議論したりしていました。夫が日本の数学を教えていたこともありましたが、IBにはIBのやり方があるということが判明したので、最終的には専門の家庭教師に依頼することになりました。日本の数学を理解しておくことは有効ですが、IB Mathはレポートが多く特殊なので、もっと早く専門の家庭教師にお願いすればよかったというのが我が家の反省点です。 |
Q5:学校や先生方とのコミュニケーションは積極的に取るようにしていましたか?
Nさん「ほとんど取っていない」
| ほとんど取っていません。娘も先生方とコミュニケーションを取るのが苦ではなかったようでSOSも出ませんでしたし。「本人の積極性もIBの評価として見られているから、保護者はあまり手を出しすぎないように」、というお話も塾の先生からあったので、学校の先生との接触は面談期間のみでした。 今振り返っても、IBについて介入しすぎない関係を実践できたのは良かったと思います。 |
Kさん「コロナもあり、あまり取れなかった」
| ちょうどコロナ禍で全てのやり取りがオンラインになってしまっていたこともあり、全くコミュニケーションは取れませんでした。また、先生とは年に2回、オンラインでの三者面談があったのですが、英語でのやり取りなので思っていることをうまく伝えられずもどかしい思いをしました。 今だったら対面授業なので、とりあえず学校に行ってみると思います。オフィスに足を運び、先生と少しずつ話したり。ちょっとずつ近づいていくことでもう少しIBや学校生活について知ることができるように行動するはずです。 |
Q6:IB生はタイムマネジメントが求められる、とよく聞きますが、この観点から保護者にできるサポートはあると思いますか?
Nさん「親は後ろから」
| 親は後ろから支える感じの方が高校生には良いのかなと思っています。 英語資格取得・大学受験・IBの同時並行スケジュールを子供ひとりに走らせるのは、とても大変だと感じたので、IBは子供に、その他はある程度親が下準備するよ、という体制が良いんじゃないかという考えです。 |
Kさん「子供自身にコントロールしてもらう」
| タイムマネジメントは結局子供(生徒)自身がコントロールするしかないものだと思います。 いつテストや課題提出があるのかなど親が把握し、細かく声かけするのは難しいです。もしくは、IBのスケジュール感を知っている家庭教師にお任せする、というのがベストだと思います。 |
Q7:お子さんの大学受験や進路決定にはどの程度関わっていましたか?
Nさん「情報収集と共有・TOEFL受験サポート」
| 大学受験に際しての志望校・学部選びについては、本人が関心を寄せている分野をヒアリングして、それが学べる大学をリサーチしました。それを本人に見せて、「ちゃんとHP見てね」と声かけをし、最終的には本人が志望校を決めました。
今の大学はやることにすごく専門性があるし、テストも難しいし、ガッツリ勉強してる感じが見ていてあるんです。だからこそ、学部選びは本人がやりたいことにすべきだと思って。その最終決定に親が関わるべきではない、と強く思います。ただ、こういうジャンル・仕事があって、こういうスキルが必要だよ、という話ができる環境を比較的広い視野を持つ私たち保護者が整えておく。その中から「あなたは何が好きなの?」と問いかけて選ばせてあげられる、というのがベストだと思っています。 あとは(帰国入試に必要な)TOEFL受験のサポートですね。長期休暇などの決まった期間に受験対策をしなければいけなかったので…..家庭教師の先生に何コマ授業をお願いするのか、いつテストを受けるのか、半年〜1年ほどの中長期的なスケジュール管理・段取りの補助を心がけていました。受験後は点数の確認をして次回受講する際のトピックを子供と一緒に計画したり、目標設定をしましたね。IB生としての活動などが忙しいので、親が「このタイミングでできること・すべきことをリードしてあげる」ということをしていました。 |
Kさん「塾選びまでは積極的に情報収集・相談」
| 日本に帰国してからの塾選びまでは親が関わりましたが、その後は塾と本人とのやりとりに任せました。オーストリアには塾もないですし、学校に日本の大学を受験する人が誰ひとりいなかったんですね。情報が入ってこないし、海外大への出願と日本国内への出願だと時期も異なるので本人もあまり把握できていなくて。それもあって海外にいる間は親も積極的に関わりました。 息子は元々明確な進路が決まっていなかったのですが、帰国後に入塾し、クラスメイトの子たちと話したりする中でやりたいことを見つけていったみたいです。 |
Q8:最後に、何かこれまで伺ってきた内容以外で話せることがあれば教えてください。
Nさん「IBの大変さを知っておくと◎」
| 親が伴走するにあたって、「IBってこんなに大変なんだ」っていうことを知っておくと良いんじゃないかな、と思います。なので、IBに少しでも興味がある保護者の方は色々なサイトや資料を駆使してリサーチすることをおすすめしたいです。情報は自分でゲットしに行ったら良いと思います。 保護者同士の繋がり(コミュニティ)があったことで、「今の時期大変そうだよね、大丈夫かな、寝てないんだけど……」と心配しつつ気持ちを共有できたのも良かったです。 |
Kさん「”IB旅行”など楽しいこともある」
| コロナ禍でなければ「IB旅行」のようなものが学校行事としてあったみたいなんです。イメージとしては、Historyを知るために〇〇に行く、Geographyで扱った場所に行く、Spanishをより身近に感じるためにスペインに行くとか。 IBは大変だけれど「そういう楽しみもある」と子供が思えるように、常にポジティブな声かけをしていくといいのではと感じています。 |
おふたりとも、ご協力ありがとうございました!
最後に
いかがでしたか?
今回はUniv-it!としては初めて「保護者の方の体験談」をインタビューし、記事化した内容をお届けしました。
今後もIB資格を活用した大学受験情報やインタビュー記事などをお届けしていきますので、お楽しみに!