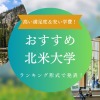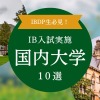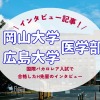【IB受験体験談】IB 43点を獲得!シンガポール国立大学 (NUS) 工学部の合格体験談

IB生にとって、アジアのトップ大学であるシンガポール国立大学(NUS)は、欧米の大学と並んで非常に魅力的な選択肢の一つです。しかし、その入試制度、特にIB生向けの選考については、募集要項だけでは分からない情報がばかりです。今回は、IB 43点を取得し、現在NUSのCollege of Design and Engineeringに在籍しているHさんにインタビューを実施しました。大学選びの経緯から、IBスコアのリアルなボーダーライン、タイトな合格発表スケジュールまで、NUS受験の体験談を詳しく伺いました。
シンガポール国立大学 (NUS) について
IB生のためのNUS入試制度まとめ
NUSの入試制度は、IB生にとってどのような特徴があるのでしょうか。Hさんの体験談と募集要項に基づき、IB生(特に5月受験生)に関連する基本情報をまとめます。
- 選考プロセス
NUSの選考(特に工学部)は、IBの最終スコアが非常に重視される傾向にあるそうです。いわゆる「コンディショナル・オファー(条件付き合格)」はなく、最終スコアが確定した後に合否が決定されます。 - 出願スケジュール(5月受験生の場合)
出願はIB最終学年の12月後半から1月後半にかけて行われます。しかし、合否の連絡はIBの最終スコアが発表される7月上旬(Hさんの場合はスコア発表の4日後)と、非常に遅いのが特徴です。 - インタビュー
Hさんが受験した工学部ではインタビューはありませんでしたが、専攻やIBスコアがボーダーライン上にある場合など、状況によってはインタビューが課される可能性もあるようです。
インタビュイーのプロフィール
今回お話を伺ったHさんのプロフィールです。
| 所属大学・学部 | シンガポール国立大学(NUS)・College of Design and Engineering(専攻: Material Science and Engineering) |
|---|---|
| 受験大学 (併願校) | NUS, NTU, アメリカの大学(複数), 早稲田大学(英語プログラム) |
| 出身高校の区分 | タイ・バンコクのインターナショナルスクール |
| 最終試験 受験時期 | 5月 |
| IB選択科目・スコア | HL: Math AA, Physics, Chemistry SL: English A Literature, Japanese A Literature, Economics 最終スコア: 43点 |
| これまでの教育歴 | 日本の小学校(小1〜3)→ フィリピンの日本人学校 → バンコクの日本人学校 → バンコクのインターナショナルスクール(中1夏〜卒業) |
シンガポール国立大学 (NUS) の受験体験談: 大学選び編
IBの科目選択はどのように決めましたか?
IBを始める時点では、まだ将来何をしたいか、どこの大学に行きたいかも全く決まっていませんでした。科目選択は、かなり「消去法」に近かったです。昔から理系科目の方が得意だったので理系に進もうと決めましたが、その中でもバイオロジーは好きではなかったので、HLはバイオロジー以外の理系科目(Math AA, Physics, Chemistry)を全て選択しました。SLも、一番理系っぽいという理由でEconomicsを選ぶなど、当時はかなり適当に決めてしまった部分もあります。
IBの科目選択は将来の大学受験に直結するため非常に重要ですが、Hさんのように「まだ将来が決まっていない」というIB生は多いはずです。Hさんの「得意・不得意」や「消去法」で決めるというアプローチは、選択を迫られる高校生にとって非常に現実的な戦略の一つと言えるでしょう。
NUSを第一志望と決めたきっかけ
併願校もある中で、受験する時の優先順位はどのように考えていましたか?
受験校の中では、NUSが圧倒的な第一志望でした。「NUSに行ければ何でもいい」とさえ思っていました。ただ、シンガポールの大学はIBの最終スコアが出た後にしか合格発表がないため、結果が出るのが7月と非常に遅いのが不安でした。そのため、学校のカウンセラーからも「それまで進学先が分からないのは不安だろうから」とアドバイスを受け、滑り止めという意味合いで、先に合格が出るアメリカの大学(8校ほど)や日本の早稲田大学も併願しました。
NUSとNTU(南洋理工大学)を比較して、最終的にNUSを選んだ理由は何ですか?
NTU(南洋理工大学)も受験し、合格もいただきました。NTUは「理工」という名前の通り理系に特化していますが、私はエンジニアリングには興味があったものの、ビジネスなど理系以外の分野にも多少の興味が残っていました。大学に入った時点で理系だけに絞られてしまうよりも、総合大学であるNUSの方が魅力的だと感じました。NUSは、どの学部の授業でも履修できる柔軟性があり、大学に入ってから色々な分野を試してみて、最終的に自分のやりたいことを決められる「選択肢の広さ」が決め手になりました。
シンガポールの大学を志望校として考え始めたきっかけは何ですか?
IBの2年目に入る前の春休み(高校2年生の終わり頃)に、両親から「シンガポールにすごいいい大学があるみたいだから、旅行ついでにキャンパス見学してみない?」と勧められたのがきっかけです。それまでは全くシンガポールの大学は意識していなかったのですが、このキャンパス訪問が大きな転機になりました。
実際にキャンパスを見て、NUSやNTUのどういった点に惹かれましたか?
実際にNUSとNTUのキャンパスを訪れてみたら、両方の大学にすごく惹かれました。特にNUSはキャンパスがとても広大で、研究室の見学もさせてもらったのですが、設備が非常に整っていることに感動しました。また、シンガポールの国自体が持つ「テクノロジーを全面的に推進している」近未来的な雰囲気も大好きになり、「ここなら勉強を頑張ってでも行きたい!」と強く思うようになりました。
大学選びにおいて、Webサイトやパンフレットの情報収集はもちろん重要ですが、Hさんのように実際にキャンパス訪れることで初めてわかる情報も多くあります。特に海外大学の場合、現地の「雰囲気」や「空気感」が自分に合うかどうかは、オンラインの情報だけでは決して分かりません。この「雰囲気」が、HさんにとってNUSを第一志望にする決定的な要因となったようです。
マテリアルサイエンスの専攻を決めた理由と高校時代の研究経験
Material Science and Engineering(材料物質工学)を専攻として選んだ理由を教えてください。
エンジニアリングの中でも、ケミカルやメカニカルのように一つの分野に特化するより、マテリアルサイエンスのように物理、化学、数学、生物といった様々な要素が詰まっている分野の方が、自分は楽しく学べるのではないかと思いました。また、マテリアルサイエンスは昔からあった分野というより、サステナビリティといった現代的な課題とも関連が深く、今まさに「熱い分野」だと感じたことも理由の一つです。この波に乗ってみるのも面白いのではないかと思いました。
高校時代にIBの課題などで、専攻に繋がるような探究活動や研究の経験はありましたか?
IBの課題とは別に、物理の論文を作成して提出した経験があります。その内容はマテリアルサイエンスに直結するものではありませんでしたが、この経験を通して「研究したり論文を書いたりするのは楽しい」と感じることができました。マテリアルサイエンスは研究室での実験が多い分野だと聞いていたので、理論中心の分野よりも、実験やレポートが多い方が自分には合っているだろうと考えたことも、この専攻を選んだ一因です。
IBのExtended Essay (EE) やInternal Assessment (IA) で行う探究活動は、単なる成績のためだけではありません。Hさんのように、論文執筆や研究のプロセスを「楽しい」と感じられた経験は、大学での専攻選びや、自分に合った学習スタイル(理論より実験)を見極める上で、非常に重要な自己分析の機会となっていたことが分かります。
シンガポール国立大学 (NUS) の受験体験談: 受験対策・出願編
NUSの選考傾向
NUSの合格には何が重要だと感じますか? IBスコアと課外活動のどちらが重視される印象ですか?
あくまで私の印象ですが、「点数しか見ていないのではないか」と思うほど、IBの最終スコアが重視されていると感じます。インターネットで下調べをした際も、NUSのエンジニアリングでIB 42点以下の合格者を見たことがありませんでした。おそらく、まずIBスコアで足切りが行われ、そこをクリアした人だけが、次にエッセイや課外活動の内容を見られる、という流れなのではないかと推測しています。
実際に入学してみて、周りの学生のIBスコアはどのくらいですか?
私が入学して、周りのIB経験者の友人と話していても、みんな最終スコアは43点、44点、45点といった高得点の子しかいません。42点以下の子にはまだ会ったことがないです。もちろん学部によって異なるとは思いますが、少なくともエンジニアリングに関しては、43点以上が一つのボーダーラインになっているのではないかと感じています。
Hさんの体感では「43点以上」がNUSの工学部における実質的なボーダーラインとのこと。もちろん公式な発表ではなく、年によって変動はあるでしょうが、NUS合格を目指すIB生にとって、IBスコアの獲得がいかに最優先事項であるかを物語っています。
出願書類の体験談 – 4つのエッセイと課外活動
IBスコア以外に、NUSの出願ではどのような書類が必要でしたか?
NTUはIBスコア以外の書類は(私の場合は)特に必要ありませんでしたが、NUSは出願ポータルサイト上で、4つのショートエッセイと、4つの課外活動を記載する欄がありました。推薦状については、IBスコアが確定する前の出願段階で提出したかは、正直あまり記憶にないです…。最終スコアが重視されるため、スコアが出る前の推薦状の比重は低いのかもしれません。
出願時のエッセイではどのようなことが問われましたか?
エッセイの質問内容は、アメリカの大学の出願エッセイと似たような、かなりベーシックなものが多かったです。「これまでの人生で直面したチャレンジは何か?」「NUSに入って何を勉強したいか?」「NUSの価値観と、あなたのこれまでの経験がどう結びつくか?」といった内容でした。IBスコア重視とはいえ、ここでしっかりと自分をアピールすることも必要だと思います。
課外活動としては、どのような内容をアピールしましたか?
記載できるのが4つだけだったので、アピールしたい活動を絞り込む必要がありました。私は、「水泳(海外遠征などの実績)」「東南アジアの数学オリンピックへの参加」「前述の物理論文の執筆経験」「学校のジャパニーズクラブでの役員経験」の4つを記載しました。
IBDPで43点を獲得した秘訣と、アメリカ大学併願のスケジュール管理
IBで高得点を取るために、勉強面で工夫したことはありますか?
実は、IBの1年目は点数が低く、やる気もあまりない状態でした。しかし、1年目の終わりに塾(EDUBAL)に入り、化学と数学を教えてもらったところ、点数が劇的に上がりました。私の場合、その塾のチューターの先輩がすごく魅力的で、「こんな人になりたい」というロールモデルができたことが、学習意欲の向上に直結しました。勉強方法というよりは、モチベーションの管理が鍵だったように思います。
IBの勉強と、アメリカ大学を含む併願校の出願準備(エッセイ執筆など)は、どのように両立させましたか?
シンガポールの大学の出願はシンプルだったのですが、アメリカの大学を8校も併願してしまったため、IB 2年目のセメスター1は本当に大変でした。IBの勉強やIA/EEのデッドラインと並行して、大量のアメリカ大学向けのエッセイを書かなければならず、常に締切に追われながらエッセイを書いていた記憶があります。
エッセイはどのように書き進め、誰からフィードバックをもらいましたか?
まずは、各大学のエッセイの質問を全てリストアップし、似たような質問はまとめて、とにかく自分で全部書き上げてみました。その後、学校のカレッジカウンセラーに見てもらい、フィードバックをもらいました。特に、ワードカウントが非常に少ないエッセイも多いため、「言いたいことを、いかに短い文字数でシャープに伝えるか」という内容の絞り込み作業を重点的に手伝ってもらいました。
IBの勉強と、エッセイが大量に必要なアメリカ大学の併願を両立させるのは、至難の業です。Hさんの体験談からも、IB 2年目の秋学期がいかに過酷なスケジュールになるかが伺えます。併願を考えているIB生は、早期からの準備と、Hさんのようにカウンセラーと密に連携して効率的にエッセイを仕上げていく戦略が重要となります。
シンガポール国立大学 (NUS) の受験体験談: 入学後・まとめ編
5月受験の場合、合格発表はいつ頃でしたか?
私のIB最終スコアの発表が7月6日でした。NTUからは4月末頃に合格通知が来ていたのですが、第一志望のNUSからの合格通知が来たのは、最終スコア発表から4日後の7月10日でした。シンガポールの大学は8月の初旬にはオリエンテーションが始まるので、本当にギリギリのタイミングでした。
合格発表から渡航までのスケジュールと、その間にどのような準備が必要でしたか?
NUSからの合格が7月10日に出て、シンガポールに渡航したのが8月3日でした。準備期間は1ヶ月もありません。その短い間に、ビザの手続きや、寮のアプリケーション(ここでもエッセイが必要でした)などを全て終わらせなければなりませんでした。ちょうどその時期は夏休みで日本に旅行中だったので、日本で慌ただしく準備を進めたのを覚えています。
これは、IBの5月受験生がシンガポールの大学を目指す上で、最大のリスクであり、最も注意すべき点です。Hさんのように、IBスコア発表(7月上旬)から渡航(8月上旬)まで1ヶ月を切るというタイトなスケジュールを覚悟する必要があります。Hさんはアメリカの大学に先に入学金を払っていたそうですが、このように「滑り止め」を確保しておく金銭的・精神的な準備も必須と言えます。
奨学金のメリットとデメリット
シンガポールの大学の奨学金制度について教えてください。Tuition Grantは利用しましたか?
シンガポールの大学には「Tuition Grant」という有名な制度があり、私もオファーをいただきましたが、利用しませんでした。これは、卒業後に3年間シンガポール国内で働くことを条件に、学費が大幅に減額されるというものです。私の周りの日本人学生は、私以外ほとんど全員がこの制度を利用しているようです。ただ、万が一卒業後にシンガポールで働かない(働けない)場合は、利息を含めて返済する必要があり、卒業時には返済額が(借りた額の)3倍近くなるという話も聞いたので、私は利用を控えました。
期待とギャップも? NUSのリアルな大学生活
実際に入学してみて、大学の授業はIBの学習と比べてどう違いますか?
大学では、高校までとは違い「講義」という形式が初めてで、ペースも比べ物にならないほど速いです。課題の量も、IBの時も多いと思っていましたが、大学も同様に(あるいはそれ以上に)多いと感じています。まだ始まったばかりですが、大学は大変だな、というのが率直な印象です。
大学の勉強で「難しい」と感じる部分、「IBと違う」と感じる部分はありますか?
一番の違いは、「自己管理」が求められる点です。高校の時は先生が「あれやってね、これやってね」と細かく指示してくれましたが、大学の教授はそうではありません。自分でカレンダーを管理し、シラバスを読み込み、計画的に学習を進めないと、どんどん置いていかれてしまうという難しさがあります。
(タイからシンガポールへの移動ですが)生活面での違いやギャップはありますか?
同じ東南アジアなので、気候には慣れており、そこは助かりました。生活面での一番の違いは、やはり「シングリッシュ」です。今でも早口で喋られると、何を言っているのか分からないことがあります。また、タイは全体的にルールが緩やかでしたが、シンガポールはルールが厳しく、罰金なども多いので、その点は気をつけて生活しなければいけないなと感じています。
サークル活動など、勉強以外の活動は何かしていますか?
いくつか参加しています。まず、高校から続けている水泳の「バーシティ(選抜チーム)」に入っています。また、昔から興味があったスポーツクライミングのチームと、サイバーセキュリティのクラブにも所属しています。勉強以外では、NUS、NTU、SMUの3大学の日本人正規生コミュニティ「ニスク(NISK)」にも入っており、非常に少ない(3大学合わせても15人ほど)日本人学生同士で交流しています。
大学の雰囲気や国籍の多様性についてはどう感じますか?
入学前は「インターナショナルな大学」というイメージを漠然と持っていましたが、実際に入学してみると、国籍の多様性はあまりないかな、というのが正直な感想です。肌感覚ですが、7割強はシンガポール人で、残りの3割の留学生も、ほぼ全員がアジア系の人たちです。欧米系の学生はほとんど見かけません。
入学前に想像していた大学生活と、実際に入学してからの「ギャップ」はありましたか?
一番のギャップは「寮生活」です。シンガポールといえば、中心街のホテルなど、とても「綺麗」なイメージを持っていました。しかし、大学の寮は、もちろん安いという理由もありますが、共用のトイレやシャワーが結構汚れていたり、部屋に虫がたくさん出たり…。これは、想像していたシンガポール生活とは少し違いました(笑)。
最後に、NUSを目指す後輩IB生へのメッセージ
最後に、これからNUSを目指すIB生の後輩たちへ向けて、メッセージをお願いします。
留学というと、アメリカやイギリスといった欧米諸国が注目されがちで、場所的にもハードルが高いと感じるかもしれません。その点、シンガポールは、アジアの文化的な近さと、欧米式の英語教育や学習環境の「いいとこ取り」ができる国だと私は思っています。英語で高度な専門知識を学びつつも、雰囲気はどこか日本に近くて馴染みやすい部分もあります。留学への第一歩として、シンガポールはとても良い選択肢になると思います。