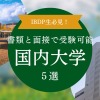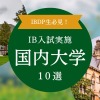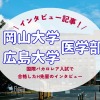【IB受験体験談】上智大学に国際教養学部入試で合格したUさんにインタビュー!

今回は、東京都にある上智大学に、国際教養学部入試で合格したUさんへのインタビューをもとに、その魅力とリアルな受験体験談をお届けします。
「海外の大学みたいな環境で学びたいけど、学費が心配…」
「筆記試験のない入試ってあるのかな?」
そんな思いを持つIB生の皆さんにとって、上智大学の国際教養学部入試は非常に魅力的な選択肢の一つです。この記事では、Uさんの体験談を通して、大学選びの軸から、具体的な出願の話まで、他では聞けないリアルな情報をお伝えします。
- 1. 上智大学について
- 2. インタビュイーのプロフィール
- 3. 上智大学国際教養学部の受験体験談: 大学選び編
- 4. 上智大学国際教養学部の受験体験談: 受験対策・受験編
- 4.1. 出願書類について
- 4.2. 出願書類の準備は、高校何年生のいつ頃から具体的に始めましたか?全体のスケジュール感を教えてください。
- 4.3. 出願にはStandardized Test Scores(SAT/ACT/IB Diplomaなど)の提出が必須です。IB Diplomaで出願したと思いますが、IBのスコアメイクで特に力を入れた科目はありますか?
- 4.4. 英語能力証明(TOEFL/IELTS)について、どちらの試験を選択しましたか?また、目標スコアはいつ頃取得できましたか?IBの英語の授業以外に、スコア取得のために行った具体的な対策があれば教えてください。
- 4.5. 約500ワードの志望理由エッセイは、国際教養学部で学びたいことと、ご自身のIBでの経験を結びつける上で非常に重要だと思います。どのような点を意識して構成しましたか?また、オリジナリティを担保するためにどのような工夫をしましたか?
- 4.6. エッセイの添削は、学校の先生にお願いしたのですか?それとも友人と見せ合ったりしましたか?
- 4.7. エッセイの中で、EEやCASでの経験をどのように盛り込みましたか?ご自身の経験が、国際教養学部での学びにどう繋がるかを説明する上で工夫した点を教えてください。
- 4.8. 推薦状はどのような先生に依頼しましたか? 先生に依頼する際に、ご自身のどのような点をアピールしてほしいと伝えましたか?
- 4.9. IB生はPredicted Gradeで出願することが多いと思いますが、最終スコアが下がると合格が取り消される可能性もあり、プレッシャーがあったかと思います。出願後から最終試験までの期間、どのようにモチベーションを維持しましたか?
- 4.10. 出願はオンラインでの書類アップロードが中心ですが、書類のスキャンやアップロードの過程で、何か分かりにくかった点や、後輩に向けてアドバイスしたい注意点はありますか?
- 4.11. 提出が求められる書類の中で、ご自身が「これは合否を分ける上で特に重要だ」と感じたものはどれですか?その理由も教えてください。
- 5. 上智大学国際教養学部の受験体験談: 最後に振り返って
- 6. 最後に
上智大学について
大学・学部の特色
上智大学国際教養学部(FLA)は、日本における国際教育のパイオニア的存在です。授業はすべて英語で行われ、リベラルアーツ教育を通じて、グローバルな舞台で活躍できる人材の育成を目指しています。
学生は多様なバックグラウンドを持ち、帰国生、留学生、日本の教育課程で学んだ学生など、国際色豊かな環境が特徴です。教員の50%以上が外国籍で、世界中から集まった優秀な教授陣から少人数で質の高い教育を受けられます。
1年次では、リベラルアーツの基礎となるコア・プログラムを通して、批判的思考力やアカデミックな英語力を徹底的に鍛えます。2年次からは「比較文化」「国際経営・経済」「社会科学」の3つの専門分野から1つを選択し、専門性を深めていきます。
国際教養学部入試について
上智大学国際教養学部の入試は、書類選考のみで行われます。入学時期は4月と9月の年2回です。
海外就学経験がない日本の高校に通う生徒でも、大学が定める出願資格を満たし、相応の英語力があれば出願が可能です。
インタビュイーのプロフィール
今回インタビューに協力してくれたのは、現在、上智大学国際教養学部に通うUさんです。
| 所属大学・学部 | 上智大学・国際教養学部 |
|---|---|
| 受験した入試名称 | 国際教養学部入試 |
| 併願校 | 上智大学(総合グローバル学部)、立教大学(理学部)、メルボルン大学、オーストラリア国立大学 |
| 出身高校の区分 | 国内一条校 |
| IBスコア | 35点 |
| IB選択科目 | SL:Japanese A, English B, Geography HL:Math AA, Chemistry, Biology |
| これまでの教育歴 | 小学校まで海外で過ごし、その後日本の高校に進学 |
上智大学国際教養学部の受験体験談: 大学選び編
上智大学国際教養学部を第一志望にしたのはいつ頃ですか?また、併願校も含め、最終的にその大学・学部の組み合わせにした理由や、大学選びの軸について教えてください。
高校3年生の初め頃には第一志望に決めていました。小学校まで海外で過ごした経験から、大学でも帰国生が多くいる国際的な環境で学びたいと強く思っていました。それが、上智大学の国際教養学部を第一志望にした一番の理由です。一方で、IBで理系科目を履修していたこともあり、最後まで理系に進む道も捨てきれず、併願校として立教大学の理学部も受験しました。
海外大学や国内の他の国際系学部(早稲田SILS、ICUなど)も選択肢にあったかと思います。その中で、最終的に上智大学国際教養学部を選んだ決め手、魅力は何でしたか?
一番の決め手は、すべての授業が英語で行われる環境です。他の大学では、国際系の学部でも教授によっては日本語で授業を行うことがあると聞いていましたが、私は徹底して英語の環境に身を置きたいと考えていました。また、オープンキャンパスに参加した際に感じた、大学全体の国際的な雰囲気やキャンパスの佇まいが自分に合っていると感じたことも大きな魅力でした。学部だけでなく、大学全体が「国際的」であることが、上智大学を選んだ理由です。
授業が全て英語で行われる「環境」を最重要視したのですね。同じ国際系学部でも、大学によって特色は様々です。Uさんのように、自分が大学生活で何を一番大切にしたいのかを明確にすることが、後悔のない大学選びに繋がるのですね。
理系の立教大学理学部も併願されていますが、文系学部とは入試形式も大きく異なると思います。対策はどのように進めましたか?
立教大学理学部の入試は小論文と面接でした。IBのHLで生物を履修していたので、その知識を活かせる生命科学系のテーマに絞って対策しました。大学から過去問を3年分取り寄せて解き、小論文の形式に慣れるようにしました。面接では、志望理由だけでなく、DNAに関する専門的な質問もされたので驚きました。質問の7割が学術的な内容で、付け焼き刃の知識では対応が難しかったと思います。IBでの深い学びがなければ、太刀打ちできなかったかもしれません。
上智大学国際教養学部の受験体験談: 受験対策・受験編
出願書類について
募集要項によると、2026年度入試の出願に必要な書類は以下の通りです。年度によって変更される可能性があるため、必ず大学の公式ウェブサイトで最新情報を確認してください。
Application Forms(入学願書)
Essay(志望理由書)
Official Transcripts(成績証明書)
Certificate of Graduation/Expected Graduation(卒業・卒業見込証明書)
Two Letters of Recommendation(推薦状2通)
Standardized Test Scores(SAT/ACT/IB Diplomaなど)
Proof of English Proficiency(TOEFL/IELTSなど)
Photocopy of Passport(パスポートのコピー)
Application Materials Checklist(出願書類チェックリスト)
出願書類の準備は、高校何年生のいつ頃から具体的に始めましたか?全体のスケジュール感を教えてください。
本格的に準備を始めたのは、高校3年生の8月頃です。上智大学の出願時期は比較的遅めでしたが、他の大学の帰国生入試やIB入試が10月や11月に集中していたため、早めに着手しました。IBの最終試験の勉強と並行して、授業の合間や放課後の時間を利用して志望理由書を書き進め、先生に添削をお願いしていました。最終試験が終わってから、上智大学の出願準備に集中した形です。
出願にはStandardized Test Scores(SAT/ACT/IB Diplomaなど)の提出が必須です。IB Diplomaで出願したと思いますが、IBのスコアメイクで特に力を入れた科目はありますか?
特定の科目を伸ばすというよりは、苦手科目をなくし、全体のスコアを安定させることを意識しました。特に化学と数学が苦手だったので、最低でも5点を取れるように重点的に対策しました。IBでは、一つの科目が突出してできることよりも、全ての科目でバランス良く得点できることの方が評価されやすいと感じています。そのため、苦手分野の克服に多くの時間を割きました。
得意を伸ばすのではなく、苦手をなくす戦略ですね。これはIBのスコアメイクにおいて非常に重要な視点かもしれません。特にIBは最終スコアが総合点で評価されるため、Uさんのように全体のバランスを意識した学習計画を立てることが、結果的に高得点に繋がるのですね。
英語能力証明(TOEFL/IELTS)について、どちらの試験を選択しましたか?また、目標スコアはいつ頃取得できましたか?IBの英語の授業以外に、スコア取得のために行った具体的な対策があれば教えてください。
TOEFLを受験しました。高校3年生の5月と9月に2回受けました。対策としては、まず1回目の受験で自分のレベルと課題を把握し、特にスコアが低かったリーディングセクションを重点的に学習しました。IBのEnglish Bの授業ではあまり勉強時間を割かなくてもスコアが取れていたので、その分の時間をTOEFLのリーディング対策に充てる、といった形で効率的に学習を進めていました。
約500ワードの志望理由エッセイは、国際教養学部で学びたいことと、ご自身のIBでの経験を結びつける上で非常に重要だと思います。どのような点を意識して構成しましたか?また、オリジナリティを担保するためにどのような工夫をしましたか?
多くの受験生が書きがちな戦争や貧困問題といったテーマは避け、自分の興味があった「医療」をテーマに選びました。ありきたりなテーマを避けることで、自然とオリジナリティが出ると考えたからです。構成としては、まず自身の原体験をパーソナルストーリーとして提示し、読み手の興味を引くことを意識しました。そして、なぜその問題意識を持つに至ったのか、その解決のために上智大学で何を学びたいのか、という流れで論理的に展開しました。
エッセイの添削は、学校の先生にお願いしたのですか?それとも友人と見せ合ったりしましたか?
学校の先生に添削をお願いしました。内容そのものよりも、日本語の表現や構成について指摘を受けることが多かったです。友人とは、お互いのエッセイを添削し合うというよりは、「どんな内容を書く?」「どの経験を盛り込む?」といったアイデアを共有する程度でした。自分の考えを整理する上で、友人との会話はとても参考になりました。
エッセイの中で、EEやCASでの経験をどのように盛り込みましたか?ご自身の経験が、国際教養学部での学びにどう繋がるかを説明する上で工夫した点を教えてください。
CASでの経験を2つ盛り込みました。1つは、エッセイのテーマである医療と直接関連する「医療支援プロジェクト」の経験です。医師や看護師でなくても、医療を支える活動ができると学んだ経験について書きました。もう1つは、サマースクールでカウンセラーをした経験です。この活動を通して学んだ「他者理解の重要性」を、国際的な環境で学ぶ上で不可欠な素養としてアピールしました。
Uさんは、ありふれたテーマを避け、ご自身の体験に基いたオリジナリティのあるテーマを設定し、CASでの経験から得た学びを「上智大学で学びたいこと」と具体的に結びつけることで、説得力を高めています。ご自身のやりたいことを効果的にアピールできたことが、Uさんの強みだったのではないでしょうか。
推薦状はどのような先生に依頼しましたか? 先生に依頼する際に、ご自身のどのような点をアピールしてほしいと伝えましたか?
DPコーディネーターの先生にお願いしました。その先生は私のことをよく理解してくださっており、CASの活動内容も詳細に把握されていたので、安心して任せることができました。「このCASプロジェクトについては必ず触れてほしい」といった形で、特にアピールしたい活動を具体的にお伝えしました。その後、先生から内容についてより詳しく質問を受け、対話を重ねながら推薦状を完成させていただきました。
IB生はPredicted Gradeで出願することが多いと思いますが、最終スコアが下がると合格が取り消される可能性もあり、プレッシャーがあったかと思います。出願後から最終試験までの期間、どのようにモチベーションを維持しましたか?
私の場合はPredicted Gradeが31点と、自分の中では悔しいスコアだったので、「絶対に本番で挽回してやる」という気持ちが強かったです。そのため、スコアが下がる心配よりも、むしろモチベーションは高かったです。プレッシャーを感じるよりも、悔しさをバネに勉強に集中することができました。出願書類の準備よりも、ファイナル試験の方が一発勝負でプレッシャーが大きかったので、試験が終わった後は逆に気持ちが楽になりました。
出願はオンラインでの書類アップロードが中心ですが、書類のスキャンやアップロードの過程で、何か分かりにくかった点や、後輩に向けてアドバイスしたい注意点はありますか?
オンライン出願はクリック一つで完了してしまう手軽さがありますが、その分、送信前の確認が非常に重要です。特に住所などの個人情報は、間違えると取り返しがつかないので、入力後は一晩寝かせて、次の日の朝に再度確認したり、保護者の方にダブルチェックしてもらったりすることをおすすめします。また、大学や学部によってオンラインでの登録期限と書類の郵送期限が異なる場合があるので、募集要項を細部まで注意深く読むことが大切です。
提出が求められる書類の中で、ご自身が「これは合否を分ける上で特に重要だ」と感じたものはどれですか?その理由も教えてください。
やはりIBのファイナルスコアだと思います。上智大学の国際教養学部は最終スコアを提出してからの選考だったので、特に重要でした。もちろん、エッセイの内容も大切ですが、ある程度のスコアがなければ、そもそも書類を読んでもらえない可能性もあると感じています。どんなに素晴らしいエッセイを書いても、スコアが低いと合格は難しいかもしれません。
上智大学国際教養学部の受験体験談: 最後に振り返って
大学選びの時に描いていたイメージと、実際に入学してみて感じるギャップはありますか?
良い意味でのギャップですが、大学の授業時間は高校時代に比べてかなり少ないです。特に国際教養学部は、一つの授業で取得できる単位数が4単位と多く、必修科目も少ないため、時間に余裕があります。IBの忙しい高校生活を経験していると、大学生活はより楽に感じられるかもしれません。自由に使える時間が多い分、自分で考えて行動することが求められます。
大学受験全体を振り返って、IBをやっていて良かったと最も感じたことは何ですか?
大学に入ってからが本当に楽だと感じることです。IBは試験勉強だけでなく、EEやCASなど、常に複数のタスクを同時進行でこなす必要があります。そのため、自然とマルチタスク能力やタイムマネジメント能力が身につきます。大学では、勉強と遊び、サークル活動などを両立させる必要がありますが、IBでの経験のおかげで、スムーズに大学生活に適応することができました。
上智大学国際教養学部の学生になって、IBでの経験が特に活きていると感じる瞬間はどのような時ですか?
レポート作成の時です。国際教養学部では、何千字ものエッセイを書く機会が頻繁にあります。IBでEEやIAを経験していると、長い文章を書くことへの抵抗がありません。周りの学生が大変だと感じている文字数でも、IB生にとっては比較的楽に感じられることが多いです。リサーチの進め方や文章構成のスキルは、大学での学びに直結していると実感します。
最後に、これから上智大学国際教養学部を目指すIB生の後輩たちへ向けて、「これだけはやっておいた方がいい」というアドバイスをお願いします。
IBで受験するなら、何よりもまずファイナル試験に全力を注いでください。上智大学の国際教養学部は、最終試験が終わってから出願まで2ヶ月ほど時間があるので、志望理由書の準備はそれからでも十分に間に合います。大学合格を意識しすぎると焦ってしまいますが、良いファイナルスコアを取れれば、結果は自ずとついてきます。まずは目の前のIBの勉強に集中することが、合格への一番の近道だと思います。
最後に
いかがでしたでしょうか?今回、Uさんに上智大学国際教養学部の貴重な受験体験談を伺いました。
Uさんのお話から一貫して感じられたのは、「明確な軸を持った戦略性」です。授業が全て英語であることを軸にした大学選び、得意を伸ばすよりも苦手科目をなくすスコアメイク、そしてありふれたテーマを避けた志望理由書の作成など、IB生ならではの多忙なスケジュールの中で、ご自身が何を優先すべきかを冷静に分析し、実行されていた姿が印象的でした。
特に、「まずはIBの最終スコアに集中する」というアドバイスは、これから受験を迎えるIB生にとって、現実的かつ力強いメッセージとなったのではないでしょうか。
IBでの大変な経験が、大学でのエッセイライティングやタイムマネジメントに直結しているというお話は、今まさにIBで奮闘している皆さんにとって大きな勇気となるはずです。Uさんの体験談が、皆さんの進路選択と受験対策の一助となれば幸いです。