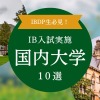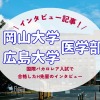【受験体験談】慶應義塾大学法学部 FIT入試の合格者へインタビュー!

慶應義塾大学法学部が実施するFIT入試は、学力だけでなく、これまでの活動経験や問題意識、将来への展望などを多角的に評価する入試方式です。まさにIBの学習者像やCAS、EEといったIBのコア要素と深く共鳴する部分が多く、IB生にとって大きなチャンスとなり得る入試制度だと言えます。
そこで今回は、FIT入試(A方式・B方式)を受験・合格し、現在、慶應義塾大学法学部に在籍するIさんにインタビューを実施しました。大学選びから、IBの経験を最大限に活かした受験対策、そして実際の試験当日の様子まで、IB生ならではの視点で詳しく語っていただきました。
慶應義塾大学 法学部について
慶應義塾大学法学部は、法律学科と政治学科の二つの学科から成り立っています。福澤諭吉の「実学」の精神を根底に持ち、単なる法律の知識や政治の理論を学ぶだけでなく、それらを社会で実際に活かすための思考力や平衡感覚を養うことを重視しています。
FIT入試について
FIT入試は、教員が「教えたい」と思う学生と、学生が「学びたい」と強く願う大学との良好な相性を実現することを目的とした総合型選抜です。偏差値だけでは測れない主体性や社会性、コミュニケーション能力などを多面的に評価し、知的好奇心と行動力にあふれる魅力的な学生を発掘することを目指しています。
A方式は、学業を含めた様々な活動で優れた実績を上げた学生を対象とし、B方式は、出身高校での学業成績が優秀な学生を対象としています。特にB方式は全国を7つのブロックに分ける「地域ブロック枠」という考え方を採用しています。選考は、書類による第一次選考と、論述試験・口頭試問(A方式)や総合考査・面接(B方式)からなる第二次選考で構成されています。
インタビュイーのプロフィール
| 所属大学・学部 | 慶應義塾大学 法学部 1年生 |
|---|---|
| 受験大学 (併願校) | なし(慶應義塾大学のみ) |
| 出身高校の区分 | 国内一条校 |
| 最終試験 受験時期 | 2024年11月 |
| IB選択科目・スコア | HL: Japanese A (7), English B (6), History (6) SL: Biology (6), Math AI (6), Economics (7) コア科目: TOK/EE(History) 1点 Total: 39点 |
| これまでの教育歴 | 0歳から9歳まで中国の現地校で学ぶ。小学4年生で日本へ移り、国際小学校を経て、国内の中高一貫校に進学。 |
慶應義塾大学 法学部の受験体験談: 大学選び編
まず、法学部を志望した理由について教えてください。
もともと中学生の頃から歴史が好きで、関連する講演会などによく参加していました。その中で、弁護士の方のお話を聞く機会があり、法律の世界の面白さに惹かれたのが最初のきっかけです。ただ、私が興味を持ったのは、弁護士や裁判官といった法曹実務家になることよりも、社会のルールである「法律」がどのように作られ、改正されていくのか、その制定のプロセスの方でした。歴史を学ぶ中で、時代と共に法や制度が変化していく様に魅力を感じ、法学という学問への関心が深まっていきました。
数ある大学の中で、なぜ日本の大学、そして特に慶應義塾大学法学部を志望されましたか?
私は中国にルーツがあり、幼い頃から日中関係や歴史、政治に触れる機会が多くありました。法律の制定に興味を持つ中で、具体的な法律の解釈だけでなく、より根源的な「法とは何か」を問う基礎法学、特に法哲学の分野を深く学びたいと考えるようになりました。そこで、法哲学の分野で指導を受けたいと思える教授陣がいる大学を探したところ、慶應義塾大学が最も魅力的に映りました。「この大学で学びたい」というより、「この先生のもとで学びたい」という明確な目標から逆算して、慶應義塾大学法学部を第一志望に定めました。
Iさんのように、特定の学問分野や指導を受けたい教授から逆算して大学を選ぶアプローチは、大学での学びをより深いものにする上で非常に重要です。特にIB生は、EEなどを通じて自らの探究心を深める経験をしているため、大学の研究者や研究内容にまで踏み込んで調べることで、志望理由に圧倒的な説得力を持たせることができるでしょう。
海外の大学や、国内の他の大学も選択肢にありましたか?最終的に慶應大学のFIT入試という進路を選んだ決め手は何でしたか?
海外大学も考えましたが、まずは日本の大学でしっかりと学問的基礎を築いてから、大学3、4年生以降に留学などの形で国外の学びに挑戦したいという価値観を持っていたので、最初から国内大学に絞っていました。そして、学びたい分野と先生が明確だったため、他の国内大学はあまり考えず、慶應一本で受験することを決めました。
FIT入試を選んだのは、IBでの学び、特にCAS活動での経験を最大限にアピールできると考えたからです。歴史や社会問題に興味がある友人と共に、校内外の人を巻き込んで講演会を企画・運営した経験は、FIT入試が求める主体性や行動力に合致すると感じました。IBでの活動実績をそのまま評価してもらえるこの入試は、私にとって最適の選択でした。
慶應義塾大学 法学部の受験体験談: 受験対策編
出願書類について
FIT入試では、志望理由書や自己推薦書(A方式)、評価書(B方式)など、複数の書類提出が求められます。
| 提出書類 | 概要 |
| 志望理由書 | 慶應法学部を志望した理由と、大学での学びが人生で持つ意味について800字以内で記述。 |
| 自己推薦書 (A方式) | これまでの活動で最も顕著な取り組みと成果を記述し、将来どのように社会貢献できるかを記述。 |
| 評価書 (B方式) | 在籍・出身高校の教員が作成。 |
| 調査書等 | 高校の成績証明書。B方式では全体の評定平均4.0以上などの条件がある。 |
出願書類の準備はいつ頃から始めましたか?IBの最終試験の勉強との両立で工夫した点や、具体的なスケジュール管理について教えてください。
本格的に準備を始めたのは、高校2年生の終わり頃、11月か12月くらいからです。A方式とB方式の両方に出願したので、並行して準備を進めました。ただ、本格的に書き込み、内容を詰めていったのは高校3年生の夏休みが中心でした。IBの勉強と両立させるため、夏に集中して書類を仕上げる計画を立てました。最終的には推敲を重ね、提出締切の1週間前まで何度も書き直して完成させました。
「志望理由」では、ご自身のどのような経験や関心を、医学への興味や将来の希望に結びつけて記述しましたか?
志望理由書では、まず「将来、法律の制定に関わる仕事がしたい」という自分のやりたいことを明確に示しました。その上で、その目標に至った背景として、高校時代にCAS活動の一環で企画した講演会での経験を具体的に記述しました。IBのプログラムの中で、自らの興味関心を社会との繋がりの中で深めていったプロセスを、将来の展望と結びつけることを意識しました。活動を通して得た問題意識を、大学でどのように学問的に探究したいかを具体的に述べました。
「自己アピール」では、ご自身のどのような個性や体験を強調しましたか?
A方式の自己推薦書では、CAS活動で企画した二つの講演会を最も強くアピールしました。一つは「入管法改正に関する講演会」、もう一つは「第二次世界大戦を経験された方を招いた講演会」です。これらの活動は、学校の先生にご協力いただきながら、企画から講師との交渉、当日の運営まで全て自分たちで行いました。約60〜80名の参加者を集めた実績と共に、社会問題に対する当事者意識と、それを他者と共有しようとする行動力をアピールしました。EEの要約文も添付し、探究能力も示しました。
「活動体験の記録」について、書いた内容や特に自信をもって書いた項目について教えて下さい。
B方式の出願には、高校の評定平均が4.0以上という条件がありましたが、私は高校1年生の時から慶應への進学を意識していたため、評定は常に高く維持するよう心掛けていました。結果として、体育以外はすべて5の評価をいただき、評定平均4.9で出願条件をクリアできました。また、提出が必要な評価書は、私のCAS活動のほとんどに携わってくださり、私の活動を最も近くで見てくださっていたIBの歴史の先生にお願いしました。先生も私のことをよく理解してくださっていたので、非常に書きやすかったと仰っていました。
書類作成に当たり、生成AIは活用しましたか? どのように活用したか教えてください。
はい、活用しました。ただし、構成や内容を考えてもらうという使い方はしていません。主に、自分で書いた文章の文法的なチェックや、より適切な語彙がないかを確認するために利用しました。段落ごとの繋がりが自然か、論理が飛躍していないかなど、文章を客観的に見直すためのツールとして補助的に使った形です。文章の骨子や熱意の部分は、すべて自分の言葉で書くことを徹底しました。
書類作成において、「歴史が好き」という自身の核となる興味を隠さず、むしろ前面に押し出すことで、より説得力のある書類に仕上げることができたようです。自分の「好き」や「知りたい」という純粋な探究心をストレートに表現することが、FIT入試では高く評価されるのかもしれません。
面接選考について
面接について何か事前情報はありましたか?
慶應義塾大学のウェブサイトで過去問が公開されていたので、特にB方式の総合考査については、どのような問題が出題されるか傾向を把握することができました。A方式の模擬講義や口頭試問は、その場で対応する力が問われるため、具体的な内容の事前情報はありませんでしたが、時事問題への感度を高めておくことが重要だと考えていました。また、周囲の受験生の多くが専門塾に通っているという話は聞いていました。
面接試験について、試験前に行った対策や準備があれば教えてください。
A方式とB方式で対策は大きく分けました。
A方式の模擬講義と論述試験は、対策のしようがないと考え、法律の専門書を読むのではなく、「法とは何か」といったテーマを扱う新書を何冊か読み、法学的な考え方の基礎を養いました。口頭試問は、いつ何を聞かれても対応できるよう、日頃から時事ニュースをチェックし、自分の意見を考える習慣をつけていました。
B方式の総合考査は、公式サイトで公開されている過去10年分の過去問を全て解き、学校の先生に添削をお願いする、という対策を繰り返しました。面接は、冒頭にある2分間の自己紹介を完璧に準備し、一言一句暗記して臨みました。
学校の先生などとどのような面接練習を行いましたか?
評価書を書いてくださった先生に、面接練習もお願いしました。昼休みの20〜30分という短い時間でしたが、入室から質疑応答、退室までの一連の流れを、ほぼ毎日練習しました。特に、「志望理由書に書いた内容から逸脱しないように、一貫性を持って答えること」を強く意識するように指導していただきました。この練習のおかげで、本番も自信を持って受け答えができたと思います。
IBスコアについて
IBのスコアに関して、出願条件をクリアするために、どのような学習戦略を立てましたか?
私は慶應義塾大学一本に絞っていたので、正直に言うと、IBの最終試験は合格に必要な点数が取れれば良い、という割り切った考え方をしていました。その代わり、FIT入試の出願時期に間に合う、8月中旬から下旬に行われるMock Examに全力を注ぎました。Mockで良い成績を収め、その結果を出願書類や面接でのアピール材料として活用する戦略でした。この戦略が功を奏し、Mockの結果を自信を持ってアピールすることができました。
慶應義塾大学 法学部の受験体験談: 受験編
「面接」について、どのような形式でしたか?
A方式の口頭試問も、B方式の面接も、面接官は教授2名、受験生は私1名という形式でした。時間はそれぞれ約15分です。B方式の面接は、まず冒頭で準備してきた2分間の自己紹介を行い、その後、面接官からの質問に答えていくという流れでした。
面接ではどのような質問をされましたか?
A方式の口頭試問では、「中国とアメリカの裁判でAIを導入する動きがあるが、これについてあなたの意見を述べよ」というテーマが与えられました。私の回答に対して、教授から次々と鋭い指摘や深掘りの質問があり、回答に詰まる場面もありました。知識と思考の瞬発力が試される、緊張感のあるやり取りでした。
B方式の面接では、驚いたことに質問の約8割がEEに関するものでした。「なぜこのテーマを選んだのか」「研究から何が分かったのか」など、非常に深く内容を聞かれました。最後に、「私たちがあなたを選ばなければならない理由は何ですか?」という、核心を突く質問をされたのが特に印象に残っています。
面接当日の雰囲気はどのようなものでしたか?
A方式とB方式で全く異なりました。A方式の口頭試問は、次々と鋭い質問が飛んでくる「圧迫面接」に近い雰囲気で、論理的に応答する力が試されていると感じました。一方、B方式の面接は非常に和やかで、時には笑い声も起こるほど雑談に近い雰囲気でした。リラックスして自分の考えを話すことができました。また、試験会場全体としては、周りの受験生の多くがFIT入試専門の塾に通っているようで、顔見知りが多く、少し孤独を感じたのを覚えています。
面接の中で最も印象に残っている質問や、回答に窮した質問があれば教えてください。
やはりB方式で聞かれた「私たちがあなたを選ばなければならない理由は何ですか?」という質問です。この大学でなければならない理由は準備していましたが、大学側から選ばれる理由を問われ、一瞬言葉に詰まりました。最終的には、これまでIBで取り組んできたこと、特にEEでの探究活動と、それが慶應での学びにどう繋がるかを必死に結びつけて答えました。
慶應義塾大学 法学部の受験体験談: 最後に振り返って
大学選びの時に得ていた情報や描いていた感覚と、実際に入学をしてみて感じることにギャップがあれば教えてください。
良いギャップと悪いギャップ、両方ありました。良いギャップは、同級生の存在です。入学前は、遊んでいる人が多いイメージがありましたが、実際には私のように明確な目標を持って入学してきた学生が想像以上に多く、共に切磋琢磨できる仲間に出会えたことは大きな喜びです。悪いギャップは、一部の授業内容です。研究者である教授の中には、授業にあまり力を入れていないと感じる方もいました。しかしその一方で、当初は想定していなかった授業が非常に面白く、新たな学問分野に興味を持つきっかけにもなりました。結果として、自分の可能性が広がるという、これもまた良いギャップだったと感じています。
大学受験の際、IBをやっていて良かったと感じたことはありますか?
良かったことしか感じません。特にFIT入試は、IBが目指している教育のベクトルと完全に一致していると感じました。探究し、行動し、表現するというIBでの学び、特にCAS活動やEEの研究が、書類選考だけでなく二次選考の面接でも中心的に問われました。IBでの経験そのものが、最高の受験対策になっていたと断言できます。IBでなければ、この合格はなかったと思います。
最後に、これから慶應義塾大学法学部を目指すIB生の後輩たちへ向けて、「これだけはやっておいた方がいい」というアドバイスをお願いします。また、実際に入学してみて感じる慶應義塾大学法学部の魅力についても、ぜひお聞かせください。
後輩の皆さんへ伝えたいことは、ただ一つです。「自分の『やりたいこと』を見つけて、それを突き詰めてください」。FIT入試とIBは、向いている方向が同じです。やりたいことが見つかれば、それをCAS活動などで実践し、EEで探究する。あとは、その経験を自分の言葉で文章にするだけです。それが自信に繋がり、二次試験でも存分に力を発揮できるはずです。小手先の知識よりも、自分の探究心と行動力が何よりの武器になります。
慶應義塾大学法学部は、授業のレベルが高く、チャレンジの多い環境ですが、それ以上に教授陣の質が本当に素晴らしいです。自分の知的好奇心さえあれば、授業後に教授に質問に行くだけで、どんどん世界が広がっていきます。知的な刺激に満ちた、最高の学びの場だと感じています。